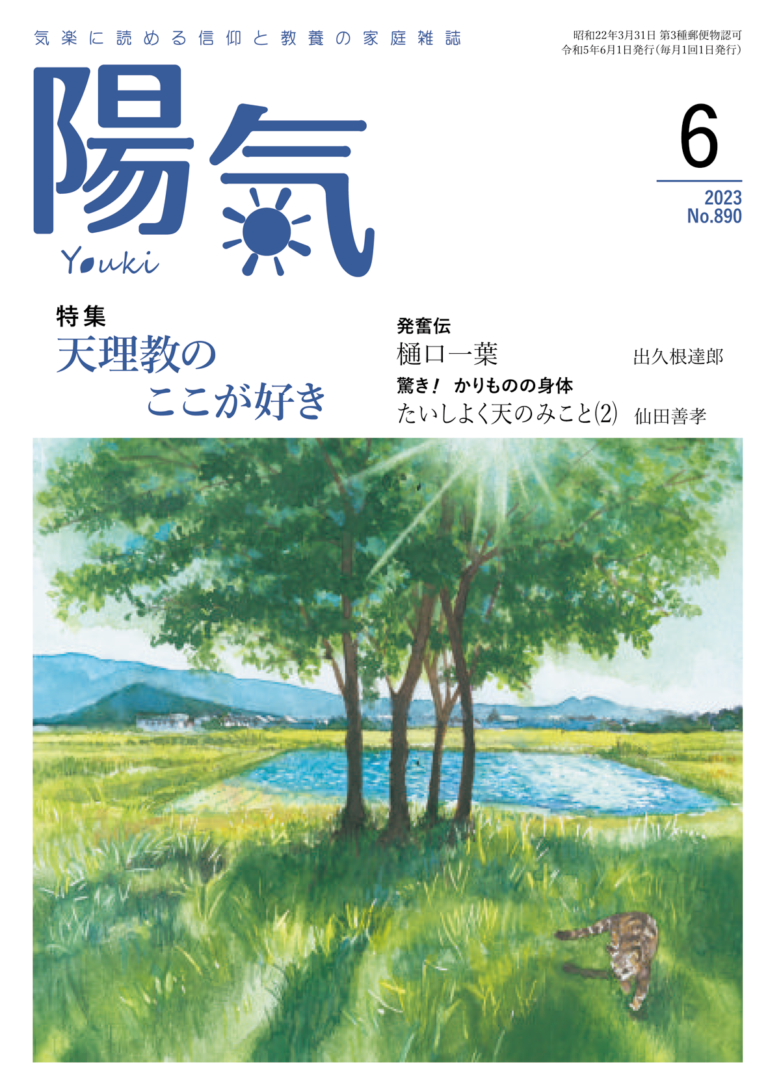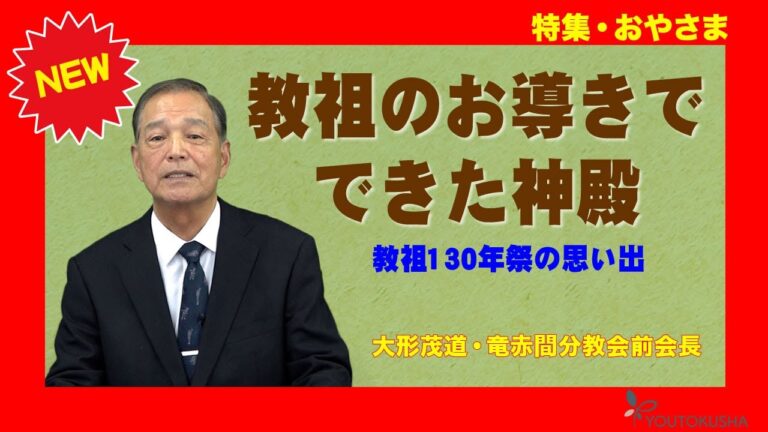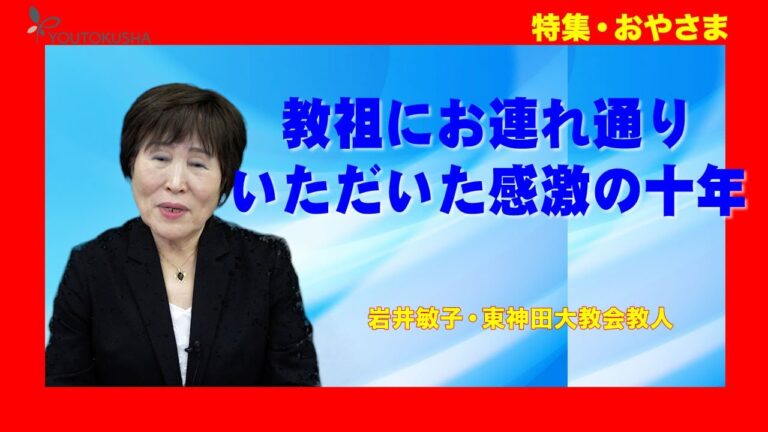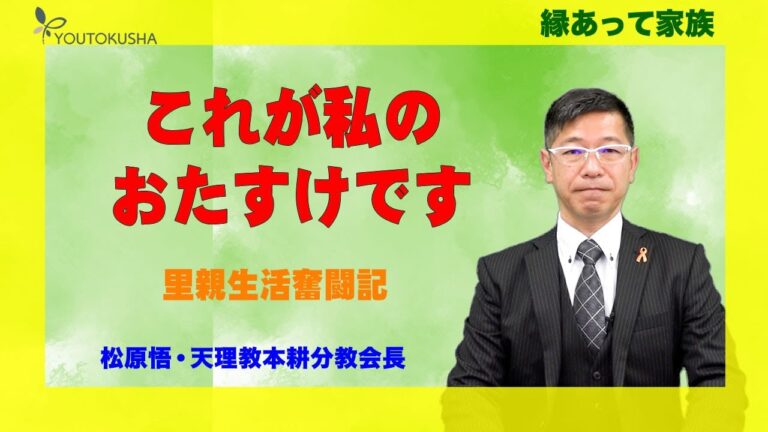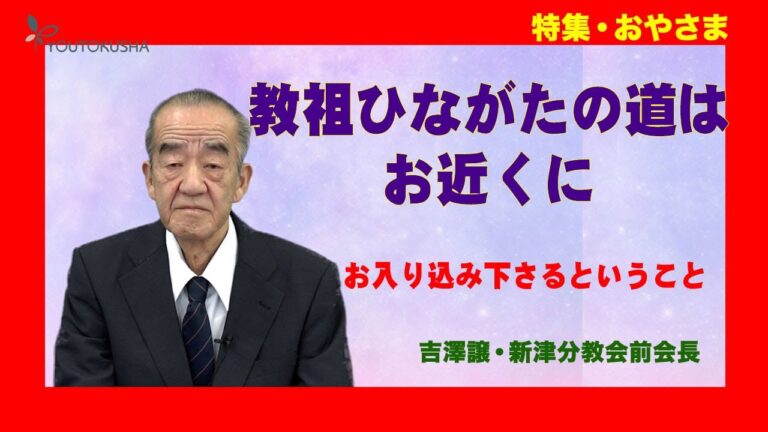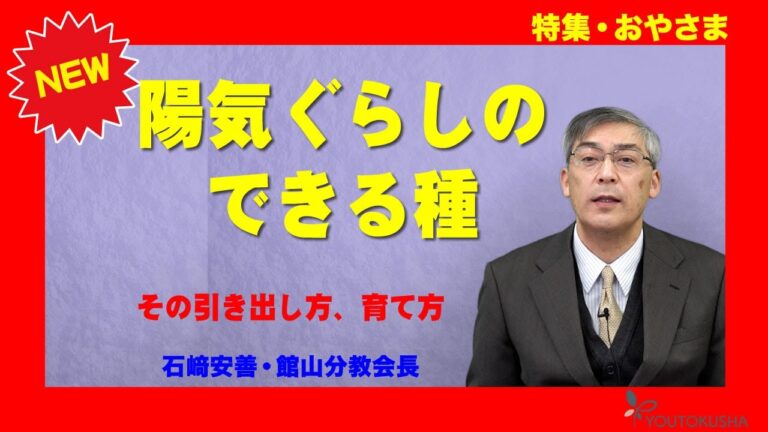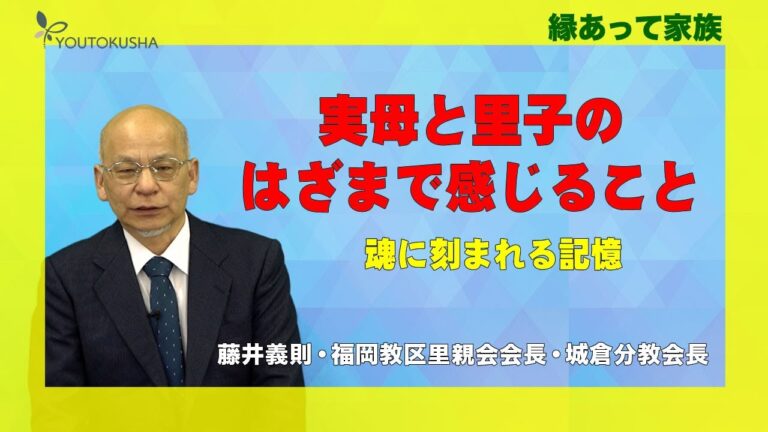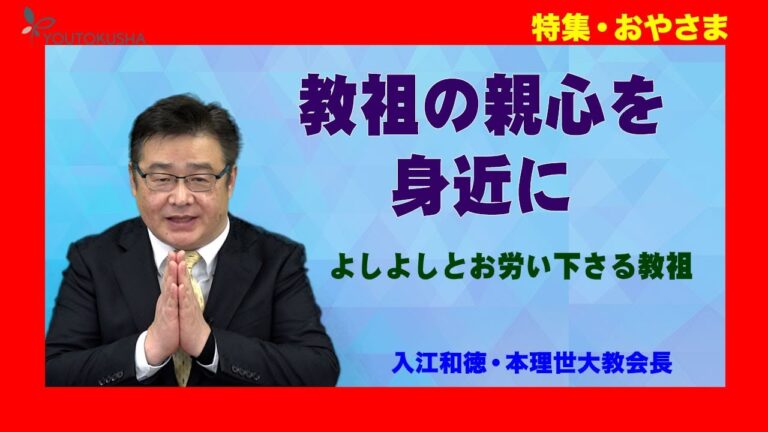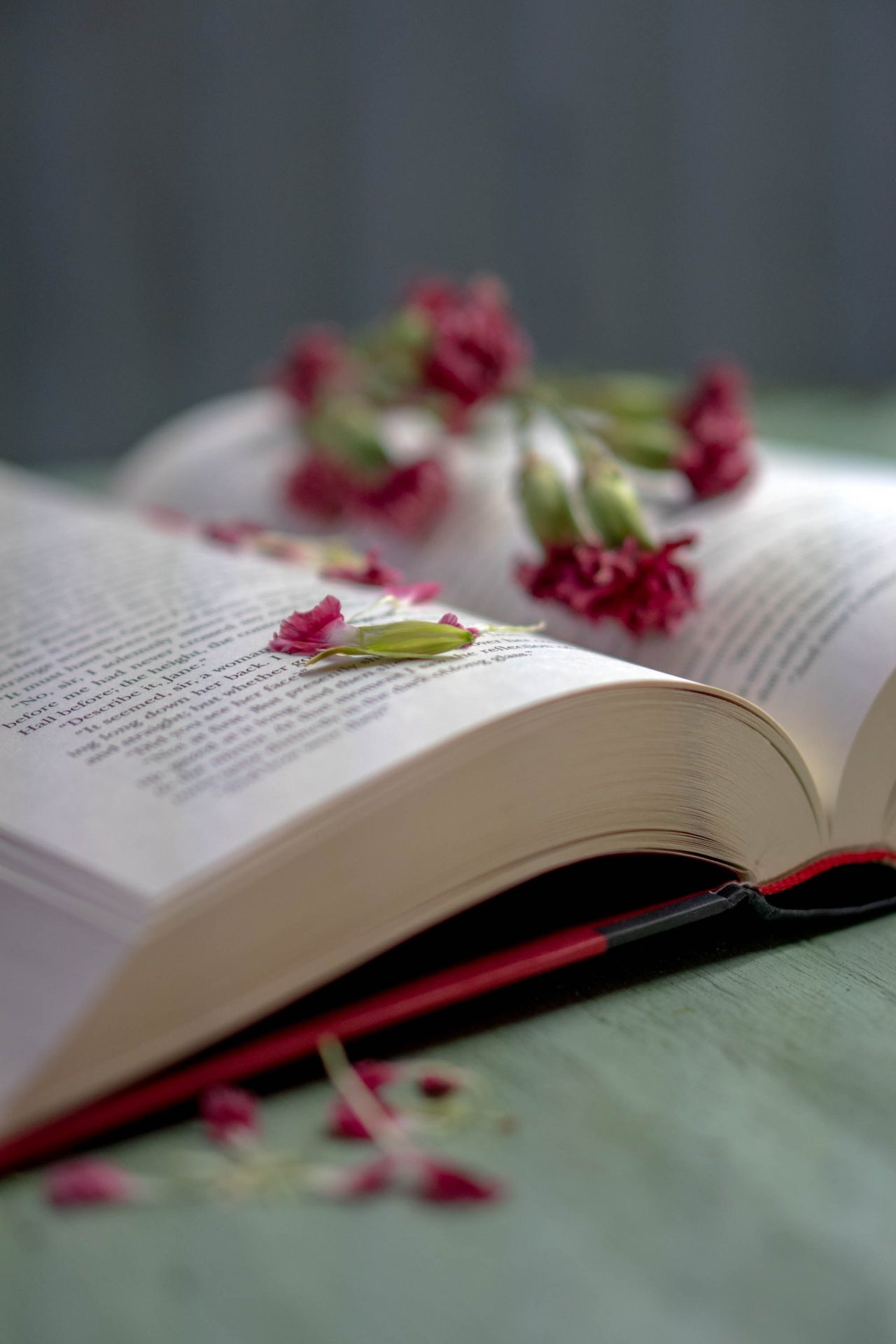2023年6月号
『陽気』6月号の特集テーマは「天理教のここが好き」。――妊娠と同時に子宮筋腫が分かり、不安で心細くて泣いた女性。学校の授業も出ず、飲酒、交通事故を起こした青年がたどった道。胃癌の疑いがある母親のたすけを願って、子どもとして心定めしたこと。尿道結石の手術か、自然に出るのを待つかの決断を迫られた話など、身上、事情の節から心惹かれた天理教の好きな教え4編。 今号の一押しは、出久根達郎氏の「発奮伝」――樋口一葉。樋口一葉が小説の師と仰ぎ、一目ぼれした新聞記者半井桃水との淡い恋心に迫る。